溶接機は製造現場や修理作業において欠かせない機械の一つですが、その故障は作業の遅延や品質の低下を招く重大な問題につながります。とくに中古の溶接機を使用している現場では、機械の経年劣化や部品の摩耗が進行していることが多く、故障のリスクが高まる傾向にあります。本記事では、長年中古機械を取扱ってきた実務の現場から得た知見をもとに、溶接機のよくある故障の兆候から、予防につながる点検やメンテナンスの基本までを詳しくご紹介いたします。溶接作業の安定と安全を守るための第一歩として、ぜひ参考にしていただければと思います。
よくある溶接機の故障とその兆候

電源関連のトラブルと初期兆候
溶接機の故障の中でも頻繁に見られるのが、電源周りのトラブルです。とくに中古機の場合、内部の電気部品や配線が経年劣化しており、電流の安定供給に支障をきたすことがあります。現場で最初に気づく兆候としては、スイッチを入れても機械が起動しない、起動してもすぐに電源が落ちる、あるいは作業中に断続的に電源が切れるといった症状が挙げられます。これらは内部の電源基板やトランスの不具合、あるいは接触不良によって引き起こされる可能性が高いです。
また、電源電圧が不安定な場所で使用されている場合、機械にとっては大きなストレスとなります。中古機械の取り扱いにおいては、導入時に電源環境の整備を確認することが基本とされていますが、現場ではつい後回しにされがちです。溶接機は精密な電気機器であるため、安定した電源供給が確保されていないと、わずかな電圧の乱れでも故障の原因となり得ます。
アーク不良や出力異常の問題
アークが不安定になる、あるいは出力が極端に弱い、または強すぎるという現象も、溶接機の故障として頻出です。これは制御基板や整流器の劣化、さらには内部の冷却機構の不調による過熱によって引き起こされるケースが多いです。中古の溶接機では、長年使用される中で排熱ファンに埃が溜まり、熱がこもりやすくなる傾向が見られます。実際に、冷却効率の低下がアークの不安定さに直結していたという事例も少なくありません。
こうした出力異常の兆候としては、溶接ビードの状態が普段と異なる、火花の飛び方が不自然、あるいは溶け込みが浅くなるといった現象が挙げられます。これらは溶接品質の低下だけでなく、作業者の安全にも関わるため、早期の対処が求められます。中古機械の専門的な視点からすると、アーク不良が発生した場合にはまず制御系統の確認と冷却系の点検が推奨されます。特に、整流器の動作電圧を測定し、カタログ値と照らし合わせることで、異常の有無を判断することが可能です。
異音・異臭による内部異常のサイン
溶接機から聞き慣れない音がする、あるいは焦げたような臭いがする場合、それは内部の部品に何らかの異常が生じているサインであることが多いです。中古で購入された機械の場合、すでに内部の部品が限界に近づいていることもあり、こうした異変は故障の前兆として見逃せません。
たとえば、トランスの焼損が進行している場合には、通電時に「ジジジ…」という異音とともに、電気が焼けるような臭いを感じることがあります。こうした異常を放置すると発煙や最悪の場合発火の恐れもあるため、少しでも異常を感じたらすぐに使用を中止し、専門の点検を受けることが重要です。中古機械の取り扱いに慣れた現場では、こうした五感による異常検知が作業者の習慣として根付いており、故障の早期発見に役立っています。
故障の種類と主な原因・兆候の一覧
| 故障の種類 | 主な原因 | 兆候・初期症状 |
|---|---|---|
| 電源トラブル | 電源盤の劣化、接触不良 | 起動しない、途中で電源が落ちる |
| アーク不良 | 整流器や制御基板の不調 | アークが飛ばない、出力が弱い |
| 異音・異臭 | トランスの焼損、内部配線の過熱 | ジジジという音、焦げた臭い |
故障を防ぐための日常点検とメンテナンスの基本

目視による外観チェックの重要性
溶接機の故障を未然に防ぐためには、日常的な点検が不可欠です。とくに中古機械の場合、外装から見えるわずかな変化が内部の異常を示唆していることもあります。したがって、作業開始前に機体の外観を目視で確認する習慣を持つことが非常に重要です。
具体的には、配線に断線や摩耗がないか、接続部に緩みや腐食が見られないか、筐体に異常な変形や熱変色がないかといった点を目安に観察します。中古機械の現場では、こうした簡易的なチェックをルーティンとして徹底することで、重大な故障の発生を未然に防いでいる事例が多く見られます。
定期的な内部清掃と冷却機構の保守
溶接機は通電時に内部に熱を持つ構造であるため、冷却機構の正常な動作が長期使用における安定性に直結します。冷却ファンや通風口に埃が溜まると、冷却効率が著しく低下し、部品の劣化を早める原因となります。中古で導入された溶接機の多くは、前所有者の使用環境によって内部に汚れが蓄積している可能性が高いため、初期点検時を含め定期的な内部清掃が推奨されます。
また、冷却ファンが正しく回転しているか、風量が明らかに弱まっていないかを確認することも大切です。とくに夏場や高温多湿な環境では冷却能力が問われるため、冷却機構の点検頻度を上げることが望ましいです。現場では、月に一度の簡易清掃に加え、年に一度の分解清掃を実施しているところもあり、それが長期的な機械の安定稼働につながっています。
電気系統の点検と測定器の活用
外観や清掃だけでは把握できない内部の状態については、測定器を用いた電気的な点検が効果的です。具体的には、テスターやクランプメーターを使用して電圧や電流の実測値を確認し、出力が仕様通りかどうかを判断します。これにより、目に見えない不具合の早期発見が可能となります。
中古機械の専門家の間では、こうした測定による定量的なデータ管理が、感覚に頼る点検よりも信頼性が高いとされています。特にコンデンサの容量低下や整流器の劣化は、外観からでは判断が難しいため、定期的な測定によるチェックが重要です。測定結果に基づいて部品の交換時期を見極めることで、突発的な故障を未然に防ぐことができます。
日誌や記録の活用で傾向を把握
日常点検の結果や異常の兆候を記録することも、長期的な保守管理において大きな意味を持ちます。たとえば、過去にどのようなトラブルが起きたか、どの部品をいつ交換したかといった履歴を残すことで、次に似たような症状が発生した際の判断材料とすることができます。
中古機械は新品と異なり、過去の使用履歴が不透明なケースもあります。そのため、導入後に記録をしっかりと行うことが、機械の健全な運用につながります。現場によっては、点検項目を一覧化したチェックシートを活用し、作業者が交代しても情報が引き継がれるよう工夫されているところもあります。こうした取り組みは、組織としての保守意識を高めるうえでも非常に有効です。
修理か買い替えかを判断する際のチェックポイント

機械の使用年数と稼働時間の見極め
溶接機の寿命や性能の劣化を見極める上で、使用年数と累積稼働時間は非常に重要な指標となります。一般的に、業務用の溶接機であれば10年以上の使用も珍しくありませんが、稼働環境やメンテナンス状況によって状態は大きく異なります。たとえば、粉塵や湿気の多い現場で長期間使用された機械は、外観がきれいでも内部の劣化が進んでいる場合があります。逆に、使用頻度が低く、定期的な点検がなされていた機械であれば、年式が古くても十分現役として活躍できることもあります。
特に注意すべきは、トーチやケーブルなどの消耗部品の交換履歴です。これらが頻繁に交換されている記録がある場合、内部回路にも負荷がかかっている可能性があるため、慎重な判断が求められます。修理に出す前に、現状の稼働時間を把握し、今後の運用に耐えうるかを冷静に見極めることが大切です。
修理費用と買い替えコストの比較分析
修理するか買い替えるかを判断する際、最も現実的な基準となるのがコストの比較です。修理費用が総額でいくらになるのか、またそれに付随する再調整や試運転の手間、部品の納期なども含めて総合的に評価する必要があります。一方で、新品や中古の溶接機を購入する場合は、導入初期費用に加えて、保証期間やアフターサポートの有無を確認することが重要です。
以下の表は、ある程度使用された溶接機において、修理と買い替えの判断を行う際のコスト比較の一例です。
| 項目 | 修理 | 買い替え(中古) | 買い替え(新品) |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 5万〜15万円 | 10万〜30万円 | 30万〜100万円以上 |
| 納期 | 1〜3週間(部品在庫次第) | 即納〜1週間 | 1〜4週間(機種による) |
| 保証 | なし〜3ヶ月(修理箇所のみ) | 3ヶ月〜6ヶ月(販売店条件による) | 1年〜3年(メーカー保証) |
| 将来的な信頼性 | 修理部位に依存 | 機種と整備内容による | 高い(新品状態) |
このように、単に金額だけでなく、納期や保証内容、将来のトラブル発生リスクまで含めて比較することで、より納得のいく選択が可能になります。特に、現場での稼働が止められない場合や、代替機の確保が難しい状況では、即納可能な中古機の導入という選択肢が現実的となるケースも多く見受けられます。
安全性と規格適合性の観点からの再評価
修理を検討する際には、機械そのものの安全性や現在の法令・規格への適合性にも目を向ける必要があります。過去に製造されたモデルの中には、現行の安全基準に照らして不十分とされる構造や部品が用いられているものもあります。たとえば、アース回路の設計が現行規格に準拠していない場合や、絶縁性能が経年劣化により低下しているケースなどが挙げられます。
現場での安全確保は何よりも優先されるべき事項であり、万が一の感電事故や火災リスクを回避するためにも、修理による延命にこだわりすぎず、必要に応じて新しい機種に切り替える柔軟性も求められます。とりわけ、複数人が交代で使用するような環境では、操作性の統一や誤操作防止の観点からも、最新機種への移行が望ましい場合があります。
中古機械取扱業者が見る溶接機の選び方と注意点

内部状態の確認と整備履歴の重要性
中古の溶接機を選ぶ際、外観だけで判断するのは非常に危険です。内部の基板やトランス、冷却ファンの状態を確認することが、良品かどうかを見極めるうえで欠かせません。特に、アルミ溶接など高出力を要する作業で使用されていた機器は、内部の熱による負荷が蓄積している可能性があります。こうした内部の状態は、実際に分解・点検を行って初めて把握できるため、表面上の清掃や塗装修理だけでは判断材料にはなりません。
さらに、整備履歴や過去の修理内容が記録として残っている個体は、状態の透明性という点で評価が高くなります。定期的な点検がされている証明がある機械は、長期的にも安定稼働が期待でき、再販後のトラブルも少ない傾向にあります。こうした記録を確認できるかどうかは、販売者の信頼性にも関わるため、購入前には必ず確認したいポイントとなります。
製造年・型式と部品供給の可否
選定時には、製造年や型式から将来的な部品供給の可否を見通すことも重要です。すでにメーカーが製造終了しているモデルであっても、一定期間は部品の在庫が確保されていることがありますが、それも無限ではありません。とくにインバータ制御型の先進的なモデルでは、専用基板や制御パーツが必要となり、数年後には入手が困難になるケースもあります。
そのため、購入前には現在の部品供給状況や、代替部品の有無、修理対応可能な業者の存在などを確認しておくと安心です。一部の業者では、入手困難な部品の在庫を独自に確保している場合もあるため、そうした背景を持つ販売者の情報を得ることが、長期的な運用を支える鍵となります。
用途に応じた適正機種のマッチング
中古機の選定において最も陥りやすい誤りのひとつが、「価格だけで選ぶ」ことです。機械選定の本質は、自身の作業内容や使用頻度に合致した機種を選ぶことにあります。たとえば、薄板のTIG溶接が中心であるにも関わらず、アーク溶接向けの高出力機を購入してしまうと、電力消費が無駄になるだけでなく、操作性にも無理が生じます。
逆に、鉄骨など厚板の施工が多い現場で小型の家庭用モデルを導入してしまうと、出力不足によるビード不良や母材への十分な溶け込みが得られず、品質面での問題が発生します。こうしたミスマッチを防ぐには、用途と機種特性を丁寧に擦り合わせていくプロセスが不可欠です。経験豊富な取扱者であれば、使用現場の状況をヒアリングしたうえで、最適な機種を提案してくれることが多いため、相談を惜しまない姿勢が求められます。
導入後のサポート体制と保証内容
中古機である以上、一定のリスクは避けられませんが、そのリスクを最小限に抑えるためには、導入後のサポート体制と保証内容の充実が不可欠です。購入時に動作確認が取れていたとしても、実際に現場で使用する中で予期しない不具合が発生することもあります。そうした際に、迅速な対応をしてくれる体制があるかどうかは、購入後の満足度を大きく左右します。
保証期間が設定されているか、またその保証が部品交換まで含まれているのか、送料や出張費の扱いはどうなっているのかなど、細部まで確認しておくことが重要です。販売者の対応姿勢は、購入前の問い合わせ段階からある程度見えてくるものですので、丁寧に対応してくれるかどうかを見極めることも、信頼できる一台を手に入れるための第一歩となります。



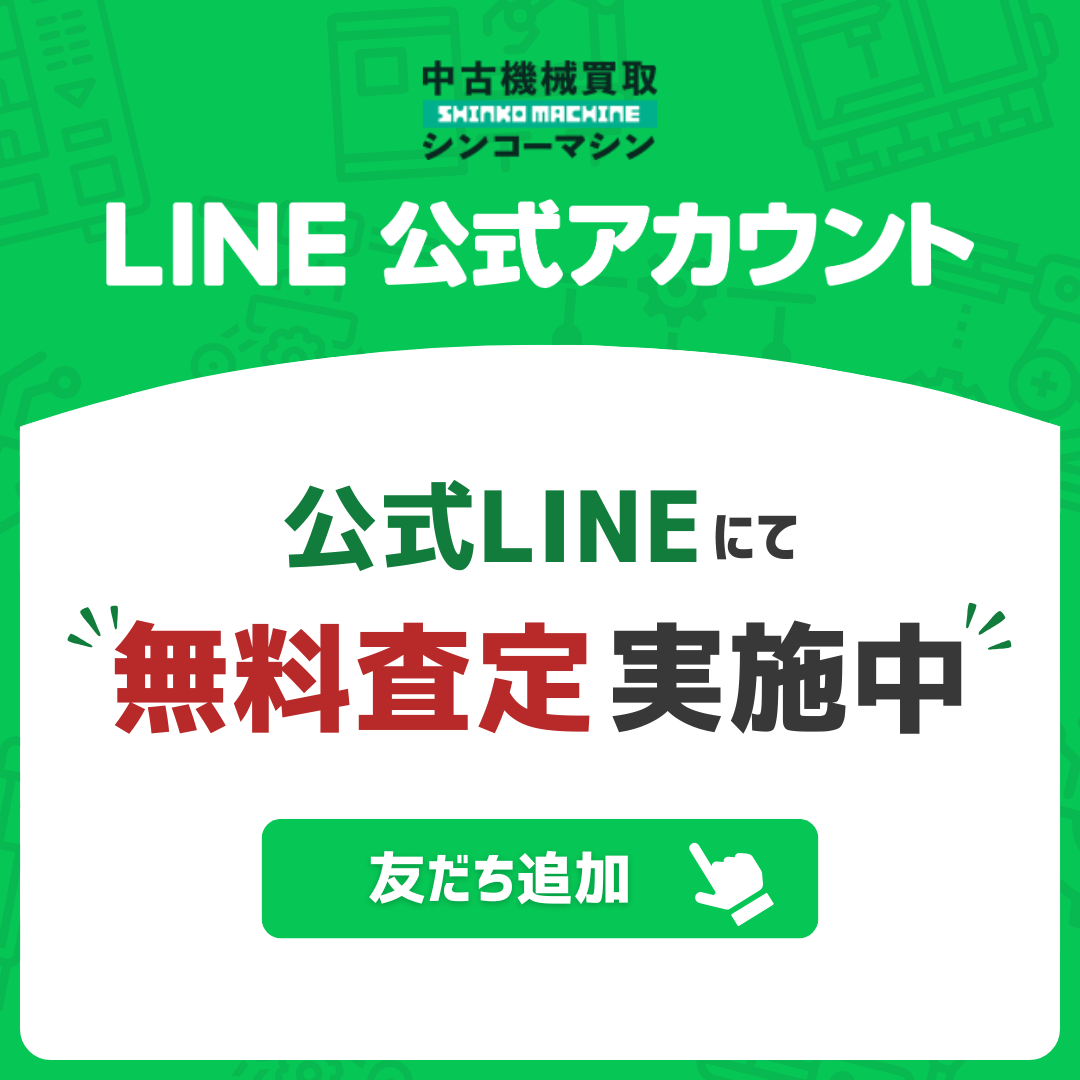
コメント